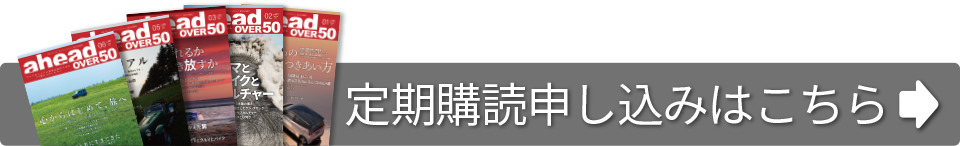シングルファーザーとして一人息子を育てているある人は、30年間勤めた会社を50代半ばにして辞めたばかり。
またある人は、中学生の頃に出会った片岡義男小説を人生の道しるべとして、真摯にオートバイと向き合い、自分の心と向き合い続ける道を選んだ。そしてある人は、15台以上のクルマと40台以上ものバイクを乗り継ぎ、ようやく最後の1台と出会えた。全ては、僕が僕であるためにー。
僕と息子とポルシェの話

先日、会社を辞めてみた。
一人息子がやっと大学に上がり、シングルファーザーとしての緊張感から解放されたことに加え、周囲の評価や期待値に忖度したからだ。しかし今年56歳にもなる自分は、あまりにも知らないことが多すぎると感じたということが大きい。
人生100年時代。どこかで必ずリセットが必要で、それが今だと直感した。
コロナ禍で無謀な決断だったかもしれない。退職後のことは全く決めずに辞めてしまった。新卒で入社してちょうど30年。最後の7年半は自動車メディアで編集長というご縁を頂き、現場主義で実際にクルマを見て、触って、乗って、聞いて、感じたことを大切にした。常にクルマとクルマのある人生の豊かさや魅力を発信し続けることに拘ってきた。天職ではないかと思うほど有意義で充実した時間を過ごせたことに振り返ると感謝しかない。世界を取り巻く自動車業界の大変革。クルマの価値の大きな変化や進化を余儀なくされている過渡期に、この仕事に居合わせたことは運命さえ感じている。ずっと考えていた。「クルマってなんだろう」と。

息子と2人暮らしという親子関係は中々緊張感がある。その息子も18歳となり、先日免許を取った。教習所での毎日の出来事を帰宅早々興奮気味に話す息子を見て、私は幸福を感じていた。7年前に10年落ちの997前期型のポルシェカレラを10年ローンで買ってから、意識的に息子とはあらゆるところに出掛けた。ドライバーである私と助手席の息子が互いに前方を向いて交わされてきた取り止めもない会話は、互いの本音が現れていて、食卓で向かい合っている時とは異なる質の会話があった。それはクルマがもつ重要な機能のひとつなのだ。理性的ではない感覚的な魂の交流が、間違いなくそこにはあった。
重度の精神疾患を抱えた母親と壮絶な幼少期を過ごした息子の心の奥にはおそらく大きなトラウマが残っていただろう。普段のコミュニケーションだけでは、それを癒してやることができなかった。非日常と言える車内で同一方向を向きながら交わされる会話は、彼の魂の浄化に一役買っていたのは間違いない。もちろんそれはポルシェじゃなくてもできたことだが、あえてポルシェという生活から解かれた空間は、息子の魂のモチベーションを上げようという私の勝手な思い込みでもある。
読者の皆様にお伝えしたい。
家族の問題や仕事での人間関係など、なんの悩みもなく順風満帆で過ごされている方などは誰一人いないと思う。みな必ず、何かしらの問題を抱えている。しかし問題が起こらないことを願ってはいけないのだ。
問題というのは常に起こる。その問題をどう解釈するかだ。解決できなくても、そこに意味や価値を見出すことができれば、幸せな人生を歩むことができるはずだ。

「あんなことがあったせいでこうなってしまったじゃないか」と他責思考するのでなく、「あんなことがあったからこそ今がある」と解釈できたとき、人間は前向きで強くなれるし、家族や他人や自分を本当に愛することができる。
境遇が変わらなくても自分の解釈次第で人生は180度変わるのだ。
クルマは、手段であり目的ではない。しかし家族や大切な人との魂の交流手段であると理解すると人生を左右する存在になり得る。クルマへの愛、家族への愛、自分への愛、全部が繋がっている。
だからこそ本当に好きなクルマに乗ってほしい。
残りの人生、あと何台のクルマに乗ることができるだろうと時々考える。もし孫ができたら、どんなクルマでドライブにいくのだろうかと。

中兼雅之 Masayuki Nakagane
赤い背表紙が僕のバイブル

オートバイはごまかしがきかないから、好きだ。ごまかしていたら、いつか必ずしっぺ返しがくる。こんなふうに、片岡義男の短編『オートバイはぼくの先生』(アップル・サイダーと彼女)にはあり、僕の心の奥にはこの一文がしっかりと書き留めてある。
〝ごまかし〟とはいったい何か? 整備不良、無謀で迷惑な運転、色々と考えられるが、ひとつ言えることは片岡小説では、オートバイが単なる機械や移動手段ではなく、物語の中心で大切に描かれている。それは精神的支柱かもしれないし、相棒、あるいはプライド。バイクのある生活が基盤にあり、いつも真摯にオートバイと向き合う。僕もそうありたいと、ずっと思っている。
今から30年ほど前。赤い背表紙の文庫本たちを、僕が兄の部屋で見つけたのは中学生の頃だった。世の中はバブル景気に浮かれ、大人たちだけなくハイティーンだった2人の兄たちも、4WDのクルマでスキーに出かけたりして、角川映画のような現実離れした、クリスタルな空気感の中に身を置いていたように思う。
「彼のオートバイ、彼女の島」や「スローなブギにしてくれ」に没頭した僕もまた、あとほんの少しだけ大人になれば、主人公たちのようなドラマが待っていると、信じてやまなかった。オートバイがあって、素敵な女性がいて、ハードボイルドで甘酸っぱいストーリーの中に数年後の自分もきっといると……。
幼い頃から「ここではない、どこかへ」と、逃避願望が僕にはあった。それは両親が喧嘩ばかりして家庭の中での居心地が良くなかったからで、オートバイに興味を持つ前は宮脇俊三の鉄道紀行を読んでは、あてもなく電車に乗って知らない町を目指した。
片岡小説の主人公たちが、オートバイで自由気ままに日本中を走ることは憧れであり、同時に知らない土地の風景を事細かく描写されていることも僕を魅了してやまなかった。瀬戸内海の島、信州、米軍基地の辺り、東北、房総……。季節は夏を特別なものとし、積乱雲が発達してひどい雨にライダーが打たれるシーンも度々描かれている。
地形や気象に興味を持った僕は、後に大学で地理学科を専攻することになり、片岡小説から受けた影響はオートバイに関することだけではなく多岐にわたった。女性に対する大人の男性の振る舞いであったり、言葉遣いなどたくさんのことを学んだ。いま思えば、どの作品も僕にとってのバイブルであり、生き方の道しるべになってきたんだと気づく。

16歳になるとすぐにオートバイの免許をとり、カワサキの並列2気筒を買う。W1かW3か……、いや中古車市場でもっとも底辺にいるGPZ250だった。スペック至上主義だったレーサーレプリカ全盛の最中、ヨンヒャク4発や2ストの最新モデルに乗る友人らからは、理解不能な絶版不人気車でしかなく、「パラレルツインの排気音はいい」と満足していた僕は、彼らからすれば変わり者でしかなかったはずだ。
18歳で限定解除し、浮気心でGPZ1000RXに3年ほど乗ったが、本当に僕が欲しいのはカワサキの650㏄だったと気付き、すぐにW1SA(1971年式)にたどり着く。以来、いくら所有するバイクが増えようとも、僕の愛車はずっとダブワンだ。キックを踏み、バーチカルツインのサウンドを聴けば、いくつになっても見える景色は片岡義男ワールドとなる。
ダブワンに乗って「ロケ地巡り」なんて言葉もない頃から小説の舞台を探してみたり、幅寄せする四輪ドライバーと喧嘩してみたり、すべてがただの真似ごとかと思っていたけれど、僕の体の中枢には確実に片岡義男イズムが宿っている。それが何なのか問われると、よくわからない。ただ、僕のハートがNOと言ったら、それに従うだけ。今日も僕はしっぺ返しがこないように、真剣にオートバイと向き合っている。
青木タカオ Takao Aoki
「僕が僕であるために」の続きは本誌で
僕と息子とポルシェの話 中兼雅之
赤い背表紙が僕のバイブル 青木タカオ
アガリのクルマに求めるコト 伊丹孝裕