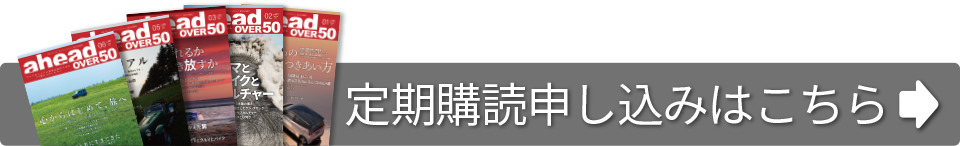取り立てて何がどうと言える町ではなかった。
どうしても行ってみたいと心惹かれるタテモノや風景があるわけでもなく、思わず財布のひもを緩めたくなるような土産品があるわけでもない。
しかし帰国して日数が過ぎるごとに、じわじわといろいろなことが思い出されては、考えに耽る時間が長くなっていった…。

KTMのエンターテインメント
オーストリアの小さな町、マッティヒホーフェンにあるKTMは、バイクの生産を開始して、来年で70周年を迎える。多くの欧州メーカーと同様、刻々と変化する時流の中で浮き沈みを繰り返し、かつては倒産も経験している。その名が消えかけたのは、昔話として語るほど古くはなく、ほんの30年前のことだ。
現在は、ラリー、エンデューロ、モトクロスといったオフロード界の王者として君臨し、ロードレースへも進出。そのトップカテゴリーであるモトGP/モト2/モト3の全クラスにファクトリーチームを送り込む唯一のメーカーであり、そこでもまた数々の栄冠に輝いている。残すは最高峰クラスのタイトルのみだ。ただ再建を果たしただけでなく、飛躍的とも言える急成長をごく短期間で達成し、「READY TO RACE」という社是を、これ以上ない形で知らしめている。
文字通り、競技ありきの姿勢をイメージさせるわけだが、その裾野はもっと広い。本当のレースじゃなくても、隣に誰かが並べば、つい競い合いたくなる。本当のアドベンチャーじゃなくても、日常を置き去りにできるような気分に浸れる。RACEとは、そういう胸の高鳴りも意味する言葉であり、KTMのモデルには、例外なくそれがある。
ツーリングに根ざしているのがBMW、レーストラックに主眼を置いているのがドゥカティだとすると、KTMの軸足はピュアなファンライディングにある。緻密さと享楽さがバランスしたモデル作りは、北はドイツに、南はイタリアに接している土地柄も無関係ではないだろう。険しい山岳地帯が国境を隔てる地では、縦横無尽に走り回れるコーナリング性能か、さもなければ、その道を外れてでも突き進める走破性が求められ、そのキャラクターを育んできた。
そんなKTMは、日本でどのようなポジションにあるのか? ’21年度(’21年4月~’22年3月)の輸入車登録台数を元にすると、シェアの大きさはハーレーダビッドソン(36.2%)、BMW(23.6%)、トライアンフ(14%)、ドゥカティ(9.3%)の順となり、KTMは6.7%でこれに続く。一方、EU圏ではまったく様相が異なり、KTMが欧州メーカーのマーケットリーダーとして他を圧倒している。傘下にあるハスクバーナ・モーターサイクルズやガスガスも含めると抜きん出た勢力を誇っているのだ。

では、なぜ日本ではその順位に甘んじているのか。本国からすれば大きな謎のひとつに違いないが、ひとえに国民性と言っていい。日本人の多くは、歴史に価値を求める。欧州の製品に対しては、特にその傾向が強い。創業が古く、由緒や血筋がはっきりしていて、語るべきエピソードがあればあるほど安心する。別の言い方をすれば、ブランド力が高いかどうかに重点を置き、他人がうらやんでくれるか否かが、ステータスになるのだ。
その意味で、KTMには若い印象を持っている。前身である1934年に設立した錠前の修理工場を含めれば90年近い歴史を誇ること、あのハプスブルグ家の末裔が経営に参画していることは、あまり知られてない。白と青が組み合わされたドイツ製のバッジや、真紅に彩られたイタリア製のカウルの前では新参者に見られているのだ。
もっとも、KTMは日本人におもねる必要はなく、そんなことは微塵も考えていないはずだ。KTMは常に未来しか見ておらず、欧米のファンはその積極性を支持している。安易にクラシックスタイルを持ち出すこともなければ、単に高級なパーツや素材で装飾したりもしない。ライダーのマインドを刺激し、ただ操ることを楽しむパートナーであろうとしている。近年のモデルで言えば、トレッキングに特化した「フリーライド250/350」、パワーではなくハンドリングを突き詰めたライトウェイトスポーツ「RC8C」などを通して、かつてないジャンルを切り開いてきた。
そしてもうひとつ。KTMの未来に対する姿勢は、キッズやジュニア向けのラインアップを充実させていることでも分かる。彼らが、ミニモトクロッサーや電動バイクで「READY TO RACE」の入り口に立ち、成長に伴って、本格的なレースへ、あるいはストリートで大型バイクへステップアップしていける道筋を構築しているのだ。こうした環境をきちんと整えているメーカーは、実のところ極めて少ない。
KTMは立ち止まることなく、先を見据えている。ブランドという架空に頼るのではなく、新しいカルチャーを創造する感度の高い人々と共に、他にない価値を築いている。
新型KTM RC390の創造力
KTMのミドル・フルカウルスポーツ、RC390が大きく進化した。MotoGPマシンから継承されたスタイリングを纏い、ミドルクラスの常識を超えた電子制御システムを装備している。また軽量化されたホイールと作動性が向上した前後サスペンションも秀逸。走り始めて特に変化を感じたのは運動性能の向上だ。減速時やバンク中の安定感が従来モデルより明らかに高まっている。アクセル操作に対してダイレクトなパワー特性は、ライダーのコントロール域から逸脱せず、スポーツライディングを堪能できる。RC390は 「READY TO RACE」を最も体現しているバイクだ。
KTM RC 390
エンジン:水冷4ストロークDOHC4バルブ 単気筒
排気量:373cc 車両重量:155kg(燃料なし)
最高出力:32kW(44PS)/9,000rpm
最大トルク:37Nm(3.77kgm)/7,000rpm

「ザルツブルクの創造力」の続きは本誌で
ザルツブルクの創造力
マッティヒホーフェンとKTM archives 若林葉子
僕がKTMを好きな
KTMのエンターテインメント 伊丹孝裕