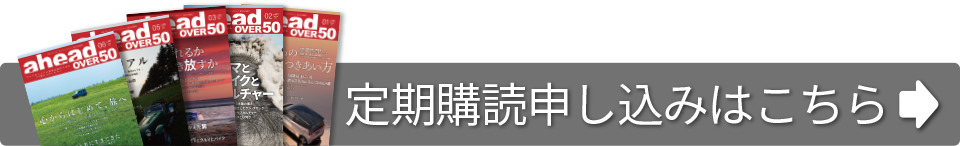「夏はただ単なる季節ではない。それは心の状態だ。」
これは、片岡義男の小説『彼のオートバイ、彼女の島』のハードカバー版の表紙と、『限りなき夏1』のあとがきに記されていた有名な言葉である。
たしかに以前は、夏が近づくと心がざわめいていた。
しかしいつの頃からか、夏という季節に気持ちが慣れてしまっている。
今年の夏は、もう一度あの頃の“心の状態”を取り戻しにいってみてはいかがだろう。


国道134号線。千葉県民の僕にとっては地元でもないし、思い出の道というほどよく走ったわけでもないのだけれど、80年代に青春を過ごした人間としては、やはり特別な意味を持っていた。まあ、いつか女の子を隣に乗せてドライブしたいという、ついに叶わなかった願望を持っていたというだけの話なのだけど。学生時代、用もないのに男同士で江ノ島あたりまでやって来て、こっぴどい渋滞に巻き込まれては「やっぱ海は千葉だよな」とお前こそが渋滞の原因になっておきながら捨て台詞を吐いてすごすご帰るという、地元の人にとっては迷惑この上ないダサ坊だったわけだ。
うらやましかったのだ。山や海や港でさまざまな表情を見せるこの道が。横須賀から葉山、逗子、古都鎌倉に江ノ島、大磯まで。多くの文学作品や映画、楽曲の舞台となってきたこの道を走れば、僕にも自分の物語が見つけられるんじゃないかと思っていたのだ。
僕がこの道を初めて意識したのは、たぶんブレッド&バターの名曲『ホテルパシフィック』を耳にしたときだ。36、7年前の話で、中学生のころだったか。去りゆく青春の日々への愛惜を歌ったこの曲は、思春期の少年には少々早かったのだけど、そんな曲を聴くだけで自分も大人になった気がしていたものだ。
この曲の歌詞には、国道を横切って浜辺に出る、という描写があるのだけど、具体的な地名は出てこない。少年時代を九州で過ごした僕には、それが実在の場所かも知るよしがなかった。後に、確か作詞を手掛けた呉田軽穂=松任谷由実がラジオでブレバタの2人とこの曲の思い出を話していて、モデルになったホテルが茅ヶ崎にあり、歌の通り国道134号を挟んで海が広がっていたという事実を知ったのだ。自分でクルマに乗る歳になった頃には残念ながらこのホテルは廃墟となっていたのだけれど、さえない青春時代のアイコンの一つとしてほろ苦く思い出す。サザンオールスターズにも同名異曲があって、やはり寂れたホテルと過ぎ去った青春の思い出を重ねた歌だったはずだ。
サザンといえば、現在の湘南のイメージの半分は彼らが作ったんじゃないかってなバンドなわけで、
こうしたイメージは、元を辿れば太陽族という言葉を生んだ『太陽の季節』『狂った果実』あたりがその原点なのだろうが、それは結果としてであって、走ってみれば一目瞭然、必然であったのだ。この道がただ美しい海岸沿いの道というだけなら、そこにドラマは生まれなかっただろう。先に書いた通り、山と海と港、そして歴史を背景にしているからこそ、この道を走る人は、自分がまるで物語の中にいるような気にさせられる。海は自由や解放、未来の象徴であり、山は葛藤や立ちはだかる困難だ。そして港は母性、受け入れてくれる場所、帰るべき場所、旅立つ場所でもある。さらに古い歴史とは自らのルーツでありながら自分を縛る因習でもあり、乗り越えるべき父性の象徴ともいえる。国道134号線を走る時、人が青春時代を追体験するような気になるのは、しごく当然の話だったのだ。
だからだろう、この道が登場する映画や音楽には、どこかノスタルジーを想起させるものが少なくない。すぐに思いつく近年の映画を並べるだけでも、『ホットロード』『DESTINY 鎌倉ものがたり』『海街diary』、どれもそれが直接のテーマではないにせよ、背景には美しい時を懐かしむ空気が漂っていた。
地元の人はまた違う意見を持つのかもしれないが、僕たちはたぶんどこかで無くした夏を見つけたくて、もう一度、あの夏に巡り会えるんじゃないかと思って、この道へ繰り出すのだ。

納車の日は、午後から雨になった。
昼前までは晴れていたのだが、海岸線に出てすぐにポツポツと降り始めた。七里ヶ浜あたりからは土砂降りの様相を呈してきたので、鎌倉から朝比奈峠を抜けて引き返すことも考えた。が、このまま帰るにしてもズブ濡れになることには変りがないと、逗子方面に向かった。葉山を通過する頃には、下着にまで雨が染みて来たので小休止するため、海に面した駐車場の電話ボックスへ逃げ込んだ。
きっかけは映画だった。高校3年になってすぐの17歳の春、何の期待もせずに観た「片岡義男」原作の映画、『スローなブギにしてくれ』が、全ての始まりだった。「オートバイ映画」といわれる割りには、レースシーンもなければ、ツーリングのシーンもない、派手なスタントもほとんどなかった。あくまでもバイクは脇役だったのだが、バイクが存在することで成立している独特の世界に強く惹かれた。映画を観たその翌日からは、『ボビーに首ったけ』、『マーマレードの朝』、『味噌汁は朝のブルース』など、バイクが登場する片岡義男の小説を読みあさった。
それまでも音楽スタジオにギターを運ぶため、という目的で原付のスクーターには乗っていた。しかし音楽少年にとってのそれは、単に便利な移動手段でしかなかった。プロテストソングに夢中だった高校生は、情熱を傾ける要素をバイクからは見出せていなかったのだ。
バイク=暴走族。昭和の時代から今も変わらない一般的な思考パターンを、その頃の自分も持っていた。大きなバイクに乗る奴らは、音と格好で周囲を威嚇し、群れることで強気になっている未熟な人間だと思っていた。だが、〝片岡ワールド〟のライダー達は違った。バイクという〝その武器〟を、自らの内面へ向かうツールにしているように感じられたのだ。そこには今の自分が求める何かがあるはず、と直感が働いた。そして中型免許を取得して走り始めた。
電話ボックスの中から雨に打たれている納車されたばかりのバイクと、雨に煙る海を眺めているのも、わるくなかった。気が付くと1時間近くもバイクを見続けていた。全身が濡れているので寒くて仕方なかったが、充実した時間だった。これから海岸線を鎌倉まで戻り、横浜に帰ってもいいし、三崎方面へ向かい三浦半島を一周して来るのも、
小説『彼のオートバイ、彼女の島』の中で、何故バイクに乗るのかを訊ねられた主人公のコオは、「退屈だからにちがいない。退屈だと、なにをやっても、自分の好きなように、どんなふうにでも適当にごまかせてしまうから。」と、返している。
「退屈だから」。バイクに乗る理由として、これ以上の完璧な言葉をいまだに聞いた事はない。

「もう少し、夏。archives」の続きは本誌で
僕のオートバイ、彼女の島 河西啓介
Dear Bobby ~小説『ボビーに首ったけ』岡小百合
夏の夜の海 嶋田智之
僕の中の稲村ジェーン 山下敦史
R134を歴史で振り返る 村上智子
SURF ROAD 134 江本 陸
ユーミンを聴いていた頃 岡小百合
全ては“スロブギ”から始まった 神尾 成
思い立って動き出せばそれは旅となる 神尾 成