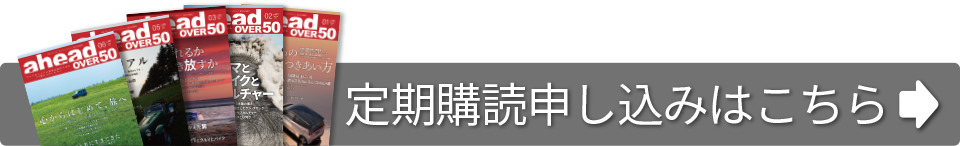2006年4月号から始まったコラムの連載は休むことなく今月号で190回目を迎えた。
「フルバンクで候」、「ローリング40’s」「ローリング50’s」と、タイトルを変更しながらも15年以上に渡った連載はahead史上最長となる。
今回は、2012年までの初期の作品から厳選した10のコラムをお読み頂きたい。

「どうして、バイクに乗らないのですか」。
十六歳から二〇年以上バイクに乗り続けている私は、ときどきこのような質問を他人様にしてみる。それも、まるで相手が納税義務を怠っていることを咎めるが如くである。彼らの反応は二つに別れる。
「最近乗りたくて堪らないんですよ~」。
「だって…危ないですから」。
前者の背中を押すのは簡単である。ちょっと撫でてやるだけで魔法にかかったように「オートバイ小僧」に戻っていくはずだ。
だが、後者の「萎縮系」はそう簡単にはいかない。だから私は彼らのために交通安全白書のこれらの数字を暗記している。
「平成十七年度の、交通事故の死傷者八千四九二人中、自動二輪の運転中の死亡者の数は五七七人だって知っていますか。警視庁のホームページに載っていますよ」。
その数字は、バイクというものを狂気の沙汰と同義語と見なしている輩たちには絶対に意外な数字のはずである。
更に加えると、同年度の夏だけの水難死亡者は四三六人、刑法犯における死者は千四百人。自殺者は三万二千人。極めつけはガン死亡者数が三二万四千人という数字である。
不謹慎を覚悟の上で言ってしまおう。
「バイクはあまり危険ではない」。
数字が語るように、実は世の中には、もっともっと怖いことが溢れかえっているのである。
「バイクが危ないという方程式で、あなたは自分の時間の価値に対して、まだゴロ寝的・誤魔化しを続ける気なのか」。
私はさらに続ける。まるで催眠術だ。
「思い描いてみてください。四月のある晴れた日曜日の朝。まだ寝ている家族を残して、あなたはピカピカに磨いた最高のバイクで東名高速を箱根に向かって走り続けている。箱根に着く頃には、頬や心の隙間を撫でていく空気の匂いがすっかり変わっていることに気がつくだろう。そして大自然の中を駆けめぐるジェットコースターのような峠に辿り着き、無理をせずに好きな速度で、好きなだけ走ればよい。でも重力に逆らうようにバンクしていくオートバイのコーナリングの魅力は、必ずあなたの心の奥に小さな闘争心を灯すはずだ。そして幾つかのカーブを抜けた先に突如として現れる、目も眩むような相模湾、そのどこまでも深く重々しい蒼さ。
あなたは思わずバイクをそこで止め、エンジンを切る。すると山の静けさが耳に張り付いてくる。バッグから自分で作った塩味だけの握り飯を取り出して食べる。喉に詰まったら麦茶を流し込もう。
磨き上げた最高のバイクと一緒に、箱根の山から下界を見下ろしていると、そこにいる自分が新橋で飲んだくれている同僚たちとは別の存在のような気がしてくる。バイクと二人だけの自分という存在が、まるで素浪人かのごとく猛々しく思えるはずだ。そんな自分にちょっと酔ってしまうのも悪くはない」。
「話を聞いていたら、乗ってみたくなりました」。
「そうですか、でも本当はとても危ないんですよ」。
「一体どっちなんですか~」。
いい大人が「遊び」でバイクに乗り続けるということは道楽ではなく決意だと思う。そんな自分であり続けようとする洒落心とも言える。だが、それがそこらのファッションとは絶対的に違う部分は、とても「危ない」ということだろう。だから本当に「危ない」ことにならないように才能と努力が必要とされる。だから、もう一度言おう。
「明日、オートバイで俺と箱根に行こう」。

ゴールデンウィークは最高の空気の中、最高の箱根を、最高のマシンで良い塩梅に楽しめた。完璧なるバイク日和。
百点満点の風の中、私たち四人と四台は飛べるようになったばかりの若いツバメのように、思うままに箱根を飛び回った。ゴールデンウィークという状況から、家族連れのワゴンや、観光バス、ハイカーなどが多いのは想定範囲内。彼らのような「社会人」に不快な思いをさせない心がけは、高校生のときから深夜の峠で走り続けてきた私たちの「社会奉仕」。
朝から午後三時くらいまで、五つの山を駆け抜けた。お昼は山の頂上のカフェで女子高生の集団のようにお喋りタイム。ただし、話している内容はファッションや恋バナではなく、新しいバイクのことや、今日は誰の乗り方が上手だの下手だの…。四○歳になろうとしている「オッサン」たちが集まって、ペチャクチャやっている姿が、周りにどう映っているのかは想像に難くない。だが居酒屋で仕事の失敗を愚痴っているときより、私たちの心拍数がはるかに高いのは確かだろう。
午後三時、渋滞が目立ち始める頃に私たちは二組に分かれて解散した。そのまま帰る二人と、芦ノ湖にある知人の別荘に泊まる私たち。
別荘にはすでに別の三組の家族が到着していた。自動車で四時間以上の渋滞を「行列」して来たと言う。子供たちも少しグッタリとしている様子だった。
その夜、温泉に入ってビールを飲んでいると、私の直接知り合いでない家族の旦那さんが話しかけてきた。
「無茶苦茶なお願いなんですけど、明日の朝、女房が起きる前にバイクに乗らせてくれませんか」
私は酔いが醒めた。その方は決して「質素」な生活をしているタイプではないと知っていた。だが、私たちのような輩にとってバイクというのは単なる百万円の玩具ではない。転んだから壊れた部分は弁償しますと言われて済む話ではない。
だが「女房が起きる前」という言葉が引っかかった。詳しく話を聞くと、彼は数年前までは私たちと同じように「乗っていた」という。
次の朝、朝風呂を済ませた私はヘルメットと鍵を持って駐車場に向かった。照れくさそうにやって来た彼は私に礼を言い、ヘルメットを慣れた手つきで被り、私のバイクに跨った。
「これは最後の油冷エンジンですよね、マフラーはチタン製に交換…」
彼はそう言うと、エンジンをかけた。チタンマフラーが発する轟音が私たち二人を一瞬にして包み込む。今の満たされた生活の中には絶対に存在しない「何か」に戸惑っているかのような彼の表情。
「そこらを乗ってきて良いですよ」
私がそう言うと、彼はエンジンを止めてヘルメットを脱いだ。
「ありがとうございました。大満足です」
彼はバイクをおりた。私がヘルメットとキーを受け取ると、駐車場の入り口に彼の妻と子供が顔を出していた。
「パパ、もうやめたんだよね」
彼の妻は不機嫌そうに呟いた。彼女の私に対する視線も決して友好ムードではなかった。優等生を夜遊びに誘ったようでバツが悪かった。
ゴールデンウィークが過ぎ去った昨夜、パソコンに彼から少し長いメールが届いていた。あの朝の私に対するお礼と、あのとき、どうしてバイクに乗らなかったかという理由が書かれていた。
「妻の制止の言葉ではなく、怖がっている自分が止めたんです」
男というモノが、自分の中の少年を追い出す瞬間に立ち会ってしまったと理解した。いつかは自分にもそんなときが来るのだろうかと複雑な気持ちになった。
バイクに乗っていると、じっと黙って私を見つめている少年と出会うことがある。泥だらけでヒザが擦りむけている少年だ。

突然であるが、今まで乗っていたセダンを売り払い、ヨーロッパの2人乗りのスポーツカーを買ってしまった。
ほとんど衝動的な買い方で、浜田山の某ディーラーに入り、5分くらいで「これクダサイ」と言ってしまった。
大して金もないのだが、実は私、クルマを買うときは、大抵はこんな感じである。財布の中身は変わらないのだから、判断だけは本能的にしようという悪あがきとも言えるが、それが健全で正しい姿だと本気で思っている。
経済的なことに関しては、最大限の英知を持ってして熟考すべきであるが、車種選びに関しては、熟考する必要など一つもないと思うからだ。
例えば子供が3人いて少し大きなワゴンが欲しいなら、『アルファード』か『エルグランド』か『エリシオン』…という選択が王道だが、その三者の差は、スペックにおいては悩む実は全くない。
全部に乗ったことがあるが、ここ10年くらいの日本車は、アマチュアが判断できる隙がないほどに大したものである。細かいスペックなどに左右されずに、本能に則していれば良いと思う。
ただし、将来の売却においてバリューが高いと予想されるのは、三社のなかで僅かに某社が頭一つ抜きん出ているという「つまらない」格差は現実にはある…。
しかし考え方を変えると、クルマを買い換えるということ自体が散財以外の何ものでもなく、自分の財布のことを考えるならば、今のクルマを大事に乗り続けることが一番である。
タクシーを見れば簡単な理屈だ、日本車はちゃんと整備すれば50万キロくらいは平気に走る。買い換え時期などという言葉自体が偽りであり、要は「贅沢」を味わいたいだけなのだ。
話は戻って、私の2人乗りスポーツカーだが、このクルマに対する仲間たちからの意外な反応に驚いている。
私としてはそれなりに誇りに感じているそのクルマのスペックや雰囲気やブランド性を誰も誉めないのだ。
「全く腹立たしい、まあ、家族がいないからね…」。
そのクルマの性能など無視したかのように、一様にバラエティー番組の突っ込みのようなことを、半分本気で言うのである。せっかく買ったそのクルマのスペックを自慢したいだけなのに…。
周りのこの反応…私にとっては全く意外なことであった。独身生活を5年以上も続けているせいなのか、クルマの存在意義において、家族を乗せるというコンセプト自体が完全に抜けていたのである。
ああ…クルマを買うことは、世間様にとってはそういうことなのだ。つまり、二人乗りのクルマを生活のメインに置くということは、かなり「反社会的行為」であるのだろう。
みんなが言っていることの言葉の裏には、実は次のような意味が込められているのだ。
「そのクルマ、買おうと思えば買えるんだよ。でも、家族を乗せられないから、奥さんが許さないんだよ」。
確かに、私がそのクルマを自慢したのは一様に、商売において「それなり」に儲けているような相手である。私の買った2人乗りよりも高い値段の、四輪駆動の外車や凄いワゴンを持っている。
ただし、それらに加えて、自分の遊び用の2人乗りスポーツカーを買い足すような「大金持ち」ではない。
現実的には買えるのに、「社会的諸事情」から諦め、その存在すら見ないようにしている「オモチャ」を自慢されたような気分になったのだろう。
これは新しいバイクを自慢したときには感じなかったリアルな反応である。バイクとは乗っていない側からみれば、その存在自体が常軌を逸脱しており、自分が乗っていることをリアルに想像できないので、羨ましいという心理にまで辿り着けないのであろう。
確かに私も、タイの島の別荘で象の親子を飼っている金持ちと飲んだことがあるが、それを羨ましいとは全く思わなかった。象に乗る日々など想像できないからだ。
「2人乗りのスポーツカー」
セダンからそのクルマに乗り換えて、初めて知ったことも多い。一番分かりやすいことで言うと、クルマとは、自分が思っている以上に、自分の本質や現状を裸にしてしまう「個人白書」のようなものであるということだ。
だからこそ、最近は、心してそのクルマを乗り回すようにしている。チョイ悪オヤジのオモチャで終わらせるつもりはない。

よく言われることだが、最近の新世代は乗り物に対してあまり価値観を置かないと聞く。景気の見通しが悪いということや、社会不安がその元凶なのだろうが、正直、その感覚というのは私たち40代にとっては理解しがたい。
「借金しても、何が何でも…買う」
そんな勢いでクルマやバイクを乗り継いできた世代である私たちは、彼らと話していて、時々ひどく面食らってしまうことがある。
社会現象であった80年代バイクブームは、当然のように当時の中学生であった私たちにも影響を与えた。
「免許を取ったら…」。
休み時間、誰かが持ってきたバイク雑誌の周りに集まり、2年後の自分たちが持つであろうバイクの話で盛り上がった。誌面を飾る、キラキラと輝くバイクに自分が乗っている姿を想像した。また、言葉にはしなかったが、まだ見ぬ未来の彼女を乗せて海まで行ったらどんな気持ちだろうかと夢想した。
高校生になると、元気な部類の男子は当たり前のようにバイクの免許を取り、中には無茶苦茶なスケジュールのバイトをして、購入のための資金を作り上げる奴もいた。金持ちの奴は親にポンと新車を買って貰っていた。
私も、バイトと親からの借金。そしてある日、仲間たちの前にバイクで乗り付ける。
「スゲー、カッコいい」。
仲間が発するその二言が乱舞する。何かが成し遂げられた瞬間だと実感した。バイト先のむかつく店長を殴らずに我慢して良かったと思った。子供ながら、きっとこういう瞬間の積み重ねが人生なのかもしれないと思った。
大学を中退し、今のステージで働き始めても同じことの繰り返しだった。充実感と同時にひどく腹の立つことも多い世界である。殴りたい奴がバイトの店長からプロデューサーやその他に取って代わっただけで、納得のいかないことや腹の立つことが8割。残りの2割を何とか資産運用しているだけ。
そんなとき、ふと、休み時間にバイク雑誌を囲んだ中学生の気持ちになるときがある。「この仕事を乗り切ったらあのクルマを買おう、さらに、あのパーツを取り付けて…」。
単なる浪費と笑われるかも知れないが、そんなことを考えるだけで、頭の上に立ち込めていたどす黒い雲の間から陽が差し込むような気持ちになる。
「乗り物」
子供の頃から、私たち「男の子」が取り憑かれ続けている、その存在。
その心理を自己分析するのなら、深いところでひどく弱々しい自分が、その物体に「搭乗」することで、それが持つ強大な力を、自分のモノにできる錯覚を持てるということだろうか…。
そう考えると、少し空しい気持ちになる。
それが出来ない、もしくはしたがらない新世代というのは、一体全体どんな空気を吸っているというのだろう。我慢できずに、バイト先の店長を殴ってしまうのではないかと心配になる。
「それぞれな感覚」
だが、先入観を捨て、新世代の彼らと深く話し合うと、実は彼らなりにそれぞれ脂ぎっていることもあるということに気がつく。だが、決定的に違うのは、私たちの世代までが持つ価値観の在り方だ。
「スゲー、カッコいい」
それだけで納得してきた私たちの世代とは違い、今はもう少し複雑なのだ。選ぶ対象がクラブ活動かバイクという、二者択一の高校時代とは状況が違う。押しつけることはない、彼らの好きなようにさせておけばよいのだ。
私なりにそんな答えに辿り着いてしまった。だが、次に思ったことは、それならそれで、こちらの世代は勝手に「悪ノリ」してしまおうということだ。
どこで話を聞いても、趣味性の強いバイクやスポーツカーを買うのはオッサンばかりだという。オッサンたちは本当は若者たちと一緒に遊び、彼らからも憧れの視線を受けたいのだが、こうなったら仕方がないのでオッサンたちだけで遊ぶことにしようと思う。
「Rolling」
その意味を問われると、それぞれに色々な思いがあるだろう。
「遊び人としてあり続ける」
私の場合はそんな言葉が出てきた。高度経済成長期を子供として駆け抜け、バブル時代に成人したこの世代はもっと自信を持って「Rolling」し続けても良いのである。
自分たちがとても稀有な時代を駆け抜けてきたことを、もっと高らかに誇るべきなのかもしれない。どこかで、今の新しい細切れの価値観体系に自らを合わせようとしているが、そんな必要は全くないのだ。
「あの世代は本当に遊び人ばかりで、どうしようもない」。
新世代からそんな風に揶揄されるくらいで、実は丁度良いのかもしれない。

映画と乗り物の関係はとても深く、切り離すことなどできるはずもない。
簡単な図式だろう。苦悩し続ける人間を、人間模様を描く文芸大作の映画も私個人としては大好きなのだが、大抵の方はワクワクするために映画を観るはずだ。
乗り物だって同じである。自分でお金を払って買った乗り物に乗っていてワクワクしない方がおかしい。それに老若男女を問わず、誰だって一つくらいは乗せてもらいたい、または操縦してみたい乗り物があるはずだ。
とにかく何かと妄想的になりやすい私も、今まで幾つもの映画とそのなかに出てくる乗り物に心を惑わされてきた。なかには人生を取り違えてしまいそうになったことも多々。
幾つか分かりやすいものを挙げてみると、オートバイならやはり『イージーライダー』は外せない。改造ハーレーでアメリカの一直線の道を突き進むことに憧れ、近所の路地裏が本当に嫌になった。
時計を捨て、バイクで遠くに向かって走りだすことが、そのまま自分の人生を解き放ってくれるという「超誤解」を世界規模で生み、実際にあの映画で人生を曲げてしまった方が何人いるのだろうか。
若き日の私もあの映画を観た後に、どこか広い場所に向かってバイクを走らせなくてはいけないと思い、取りあえず日本で思いつくのは鳥取砂丘だと、二日かけてその地に向かったのだが、現地に着くと鳥取砂丘はバイク走行が禁止で入れて貰えなかった。帰りに雪が降ってきて散々な目に遭った「自由への疾走」であった。
未だに朽ちることのない毒を持ち続けている危険な名作ナンバーワンだろう。
自動車なら「007シリーズ」の一連のボンドカーだ。マッハゴーゴーにも通じる、男子垂涎のギミック祭、全開である。
私自身、実際に自動車に乗っていて、一日に何度かは自分のクルマのハンドルのボタンを押して、あの手の秘密兵器が装着されていないだろうかと考えてしまう。
同映画の新作を観る度に馬鹿馬鹿しいのは分かっていても、新しいボンドカーが出てくると否応なしに身体が反応してしまう。
最近ではアストンが活躍しているが、やはり、一番度肝を抜かれたのは『私を愛したスパイ』のロータス『エスプリ』が潜水艦に変わってしまうものだろう。あれを観た小学生の私は絶対にロータス『エスプリ』を買ってやると誓った。
流石にローンで買った数百万のものを、潜水艦になるはずだと信じて東京湾に飛び込ますことはなかったが、海沿いを走るたびに水面に向かってハンドルを切ってしまいそうな妄想は途切れはしなかった。
飛行機なら文句なく『トップガン』だ。同映画に出てくるカワサキ・ニンジャも有名ではあるが。
何と言ってもF-14・トムキャットのアフターバーナー全開である。かのヒット曲デンジャーゾーンと共に大空に向かって全開で飛び立つトムキャットをスクリーンで観た高校生の私は、頭のネジが数十本弾け飛んだ。映画館を出るや、私は本気で航空自衛隊に入隊しようと考えた。
次の日、学校に行き、恩師に大学受験をぶん投げ、高校を出たらそのまま「航空自衛隊航空学生」に進みますと言った。
困り果てた恩師は親に電話をし、私はその夜にオヤジにしっかりしろと殴られた。落ち込んだ私は仕方がないので大学に進み、小説と芝居を始めたのだがそれが正しい選択だったのかは未だに不明。
こうして私が好きな映画とそのなかの乗り物たちを振り返ると、要するにほとんど幼児性の塊であり、仮面ライダーごっこをしていた幼少時代から何一つ変わっていない事実を自分で納得した。
反省したいところなのだが、きっとこれからもそんなことを続けていくような気がして仕方がない。

最近、巷で「ターボ」という言葉を聞くことが少ない。とくに子供たちの口から聞くことなどは皆無と言って良いだろう。
私の記憶では、日本に「ターボ」という言葉が浸透したのは、四十二歳の私が中学生の頃だったと思う。調べてみると、日本初のターボエンジン搭載車は1979年に発売された日産セドリックとグロリアであるから、その記憶も正しいということだろう。
1974年から1978年、池沢さとし氏「サーキットの狼」が連載されたことなど子供たちの間で巻き起こったスーパーカーブームの影響もあり、あの頃の子供たちの頭の中は半分くらい「乗り物」のことで占領されていた。
そんな子供たちが、TVコマーシャルや町中でクルマのエンブレムなどに見る「TURBO」という仰々しい文字に反応しない訳がない。クルマのエンブレムの横に輝く「TURBO」という文字に憧れ、いつかは自分もターボに乗ると誓ったものだ。彼らはその英語の意味や、機械としての構造、形を知らずとも、その本質的なイメージを理解していた。あの時代の子供特有の本能とも言えるだろう。
当時の私たちは、自分の力をパワーアップさせるという「魔法」のような雰囲気から「ターボ」という言葉を何かとよく使ったものだ。「TURBO」というロゴのステッカーシールも沢山発売され、鞄や机に意味もなく貼り付けた。
「ターボで行くから」
「ターボで勉強する」
「ターボで食べる」
「ターボで…」
要するに、「より多くの空気と燃料を燃焼させて出力を上げる機械」という本来の「過給器」の意味とは無関係に、物事の数値を強烈に上げたり、強烈な状態そのものを意味する象徴的な俗語として使われてしまったのである。
一時は学校中の男子たちが、何かと「ターボ」という言葉を連発したものである。
これは毎年何か新しいことが始まり、毎年事に全ての製品スペックが向上していたような、あの時代が求めていた「高揚感」と言葉の雰囲気がマッチしていたからだろう。
実際に初めてターボ付きのクルマに乗ったのはサバンナであった。高校生のときに先輩が持っていたもので、助手席であったが、加速の途中から「ヒューン」と音がすると同時に、強く加速感が増すことが記憶に鮮明に残っている。
今で言えば古めかしい二段階的な加速であるが、途中から急激に盛り上がる加速感に驚いた。だがそれはずっと勝手に思い込んでいた、ターボという言葉のイメージ、強い高揚感とはまるで違い、単なるクルマの急加速でしかなかった。
昨今の「エコ」とまったく同じ使われ方と言えるかも知れない。
「エコな奴」
「エコ人生」
「エコな性格」
「エコな…」
こんな言葉を普通に使っていることが多いが、これだってターボの間違った使われ方と同じだ。本来の「環境に配慮する」ということに加えて、「節制、節約」「大人しい」というような雰囲気の言葉として使われることが多くなってしまっている。
言葉とは生き物であり、時代や風俗を主食に成長変化していくのは当然であるが、とくにエコという言葉の使われ方に関しては、ちょっと「?」 と思い、ターボの勘違いの再来だと苦笑してしまう。
「環境に配慮する」ということは実はとてつもなく困難で、機械の出力を上げることよりも難しい。今の時点の文明レベルではどんなきれい事を並べても、基本的な経済活動そのものが化石燃料に大きく依存しているので、まだまだ「ターボ」である。
エコロジーを目指さなければ文明そのものの危機に陥るということは明白であり、全ての人が「エコ」を意識するのは義務であろう。その前段階としての言葉遊びのなのは分かっているが、言葉で遊んでいるだけで、本質的な危険を誤魔化しているような気がするときがある。
それは「ターボ」な時代を過ごしたからこその直感だろう。

以前ここで書いたことがある「オープンカー」をこの秋に売却してしまった。理由は大したことではない。車検を通す気合いがなくなったことと、飽きのサイクルが重なっただけだ。そして現在新しいクルマを物色中である。
売却後、新しいクルマを手に入れるまで、1ヶ月くらいの「車レス生活」を送るというやり方をするのは、ここ10年くらいの慣習だ。大抵の方は「車レス生活」になってしまう期間を作らないために、今のクルマを乗りながら新しいクルマを探すというやり方をするのは当然だろう。
だが捻くれ探求者の私は、次の自分が一体どんなクルマを欲しがり、それで何をやるべきかを知るために、買い換えのタイミングで、あえて修行じみた「クルマレス生活」を体験することにしている。
言ってみれば健康目的の断食道場のようなもの。あえて飢餓状態に自分を追い込むことにより、飽食な状態により曇っていたビジョンや感覚をクリアーにするということだ。
仕事でも使うから大変じゃないですか、と心配されることもあるが、東京の場合、「なければない」で意外と何とかなってしまうという「驚愕の真実」に出会うことになる。
また雨さえ降らなければバイクという選択肢もあり、いつものサイクルと違う自分を体験できる良い機会だと、変化そのものを楽しむようにしている。
駐車料金やガソリン代が掛からない生活というのもシンプルだなあと感じる反面、その分、公共機関による帰宅途中に赤提灯…という選択肢も増えてしまい、この生活スタイルがお財布と健康に優しいかは少し疑問が残る。だが結果として、断食道場的な「クルマレス生活」を体験すると、自分におけるクルマの存在意義や、人が乗り物で移動するということの意味を考えるようになるのは確かだ。
どんなタイプのクルマを持った方がより自分の人生が豊かになるのか、またはクルマの本当の正しい使い方を考えるようになる。
「近所のスポーツクラブまでクルマで行き、そこでランニングマシーンで走るということは、エアコンとストーブを一緒に使っているのと同じくらい愚かな件」
「真夏の三連休、行楽日和全開にクルマで湘南や伊豆に飛び込むのは、小さな子供がいる家族連れ以外は愚かな件」
「都心には、駐車場代がタクシー料金より高い場所がある件」
反対にクルマがないと、美味しくないことが何なのかが見えてくることもある。
「テレビ局の入り口に駅から徒歩で向かうと、何故だか微妙に格好がつかない件」
「深夜はガラガラでさらに安い、郊外型シネコンのレイトショーに行けない件」
「ETC休日千円システムでのB級グルメツアー。クルマがないと結果としてB級にならない件」
半分冗談のような件もあるが、他にも「クルマレス生活」を体験するからこそ見えてくる「仕分け」があるのは確かだろう。大好きで楽しい乗り物なのだからこそ、正しい使用法を知っておくべきなのだ。
そんな私が現在考えている次なる選択、「見栄を廃し、外側は小さいながら中身は大きい」ということが一つのキーワードになっている。
これは仕事でレンタルしていた、ある軽自動車に半日乗っていて感じたことだ。軽自動車に乗る機会がない方は、おそらく昨今の軽自動車の進化に驚くはずである。
下らない「昭和の見栄」を廃して考える限り、普通の移動において、あれ以外の選択はないと言い切って良いくらいに今の軽自動車は良くできている。さらに中が普通に広い。多分黙って乗せてしまえば、軽自動車と気が付かない方がほとんどだろう。
結局、その体験から私が感じたのは、自分は「マイカー」で何を移動させたいかということだった。
代表的な車種のイメージを挙げるとすれば、アバルトバージョンのフィアット500的なものだ。「見栄」を移動させたいのか、住居並みの「居住性」を移動させたいのか、マシンという「快楽」を移動させたいのか。それを分からずして選択してしまうのは、愚かとは言わずとも、無駄遣いと言っても良いだろう。
今の時代、本当に良い物は、己の小さな見栄の陰に隠れている。

真夏が近づくとどうしても、高校生の頃に同じクラスのAチャンと初めてバイクで夜中の湘南に向かった夜のことを思い出す。高校生同士が夜中にバイクで「異性交遊」ということがモラル的にどうかと聞かれても30年近く前のことなので時効成立だろう。
互いに親に秘密で自宅を抜け出し、多摩川の土手で待ち合わせて246をひたすら南下した。
私のマシンはヤマハの200㏄のオフロードバイク。
今でこそ、図々しい不良中年となり、女性と夜中にクルマを走らせるなんて大した行事ではない。そこで二人の間に流れる時間や空気感の大抵は予測可能。
だが、高校生になったばかりの自分にとって状況は全く違っていた。熱帯夜、246の光の流れの中を好きな女の子と身体を密着させ、見知らぬ海沿いに向かう。その行為と自分の中を流れた時間というのは、映画や漫画の中のものが具現化したようなものであり、ほとんど現実感のない「トランス状態」であった。 脳生理学的にいえば、色々と危険な物質が分泌しっぱなしであったのだろう。
汗ばんだTシャツが通り過ぎていく夏の空気に溶けていき、何も深く考えていない、何も深く考えなくて許された夜だった。確か茅ヶ崎の砂浜で手をつないで歩いたのがその夜の最大イベントだ。
いつしかそんなAチャンとも別れを経験し、クルマの免許を取得して、親のクルマをどら息子らしく乗り回すようになり、いつしか熱帯夜の逃避行も忘れてしまった。ひょんなことから今の世界に飛び込み、バブルの大騒ぎも一通り観覧した。そこから再び時間はどんどん過ぎて、娘も産まれ、そこそこ不良なオヤジになってしまい…、震災で日本の「腰が抜け」、そして今という夏を再び汗ばんで生きている。
この夏は不思議な夏である。やはり震災が私たちに残した大借金とトラウマは計り知れない。だが、それでも日本という島はそんな人々の気持ちと関係なく四季が過ぎていく。まだ肌寒さを感じていたあの3月から、ほんの少ししか時間は経っていないし、大きなことは何も解決していないというのに、気が付くと大粒の汗をかく日も珍しくない。
そんなAちゃんがフェイスブックで私の名前を見つけたらしく、海外から久々にメッセージを送ってきてくれた。聞くと海外に移住して向こうで子供を三人育てているという。放射能は平気かと聞かれたので、本当のことは誰にも分からないが、自分の娘を含めた子供たちにこんな夏を体験させてしまった大人たちの愚行を恥じているとだけ伝えた。
他人行儀なメッセージの交換をひととおりした後、久々に夜中の国道をバイクで走ってみた。夏の始まりを予感させる湿気を含んだ空気をあの頃の6倍の排気量のバイクで切り裂いてみたが、もうあの頃のような「トランス感」を自分が求めていないことを再確認するだけだった。
夏の到来というのは、どうしてか年齢を重ねるごとに、過ぎ去っていった幾つもの夏のそれぞれの横顔を思い出させる。今年の夏はその中でも、大きく自信を失ったこの国の新しい始まりのファンファーレとして記憶に残るのだろう。
だが、この夏の到来は、絶対にこのまま斜陽に甘んじていくだけでは済まさないという気持ちを、「大人たち」が新たに持つチャンスになるかもしれない。
私を含めて、今回の震災で「生きる」ということを改めて考え直した方は多いと思う。善良な方の努力の積み上げが一瞬にして霧散してしまう、無慈悲な現実を幾つも目の当たりにした。思考停止にも陥った。
だからこそ、この夏は大汗かいてのたうち回り、何が大事で何が要らないかを再び考え直そうと思う。そういう意味では猛暑の夏が来たことは悪いことではない。人は寒いよりも暑い方が、血湧き肉躍るときが多いはずだ。自分たちに起きてしまった現実と、これからの生き方を、日焼けと共に己に染み込ませることができれば、来年の夏はもう少し違う気持ちで迎えられる可能性もあるだろう。
Aちゃんと湘南にバイクを走らせた熱帯夜、あんな気持ちになることはこの先ないかもしれないが、今から諦める必要もないはずだ。

新しいスポーツカーと大人たちの関係を探しているかのように、ハチロクとBRZが盛り上がっている。予約も一杯ですぐに手に入るような状況ではないという話も聞く。またメーカー自体が合法的な改造を推進しているのが興味ある動向で、改造パーツ専用の分厚いカタログもあるくらいだ。個人的には良い流れだと思う。ちょっとした改造でも犯罪者扱いされた時代を知っているだけに、ディーラーがマフラーやサスペンションやエアロバーツを売ったりするのは、何とも隔世の感がある。
このクルマのコンセプトに、若者のクルマ離れに歯止めというような文句があった。だが、実際に元祖ハチロクを18歳や20歳で長いローンを組んで手に入れ、無茶苦茶な改造をしていた、昔の若者である私たちからすると、「違和感」があるというのが正直な気持ちだ。私はここに噛みつきたくなった。上辺の話はやめてほしい。もっと正直に言えばよい。
「あの頃の走り屋青年、カムバック。子供の学費や家のローンなんて気にするな」。
このクルマ、ハッキリ言ってそれ以外に何のコンセプトがあるというのだろう。こんなので家族旅行も出来るわけがないし、奥さんがマニュアル免許を持ってないから車庫の入れ替えも地獄絵図、狭いリアシートで子供がアイスクリームをレカロシートの縫い目になすりつけて父が発狂するのがオチである。もっと金持ちオジサンはBMWのM3かZ4を買う。
繰り返すが、ハチロクが欲しくて改造しまくりたい私だからこそ、ハッキリ言わせてもらう。そして前ハチロクを主役にしたDVD映画も実際に企画主演している立場であるからこそ、愛の暴言を言わせてもらう。
ハチロクを買って改造する若者がいないとは言えないが、そのコンセプト自体が私たち直撃であり、それ以外の何者でもないのだ。
その世代をリアルに体験している私なので正直に書くが、あの時代、ハチロクに限らず、スポーツカーを若くして無理に買って、さらに改造などをしていた若者たちは、ほとんどが建設関係や職人系の人間だった。時代を表すように、彼らは月給50万くらい貰う者も少なくなかった。
実際に私の仲間でも、20代前半に限っては、特殊な例を除いて、大学を出て一般企業に就職をした仲間より、建設や職人系で頑張っている仲間の方が派手に金を使っていた。
また彼らの金の使い方というのが、江戸時代の職人たちの言葉にあるように「宵越しの金は…系」な金銭感覚な場合が多かった。給料の半分以上をクルマと改造費のローンに充てることも珍しくはなかった。ローン会社の審査も甘く、そんな若者に300万くらいのローンを平気で組ませていた。
良い悪いではなく、実際にその時代のチューニングカー業界にドップリ関わっていた私の周りにはそういう風景が幾つもあった。私も含めた、そんな金銭感覚な輩たちに日本のスポーツカーのチューニングシーンは育てられたと言っていいと思う。
そんな世代が少し元気がない時代である。だからこそ堂々と「こいつで、また無茶苦茶しようぜ」と正々堂々言えばよいのである。あのクルマを若者に買わせて改造しろということ自体が、今の日本が抱えている病魔を象徴しているとしか思えない。脂ぎって太って禿げたけど、あのころの青年よ、今こそカムバック、ローンの金利も安くするぜ、と堂々と言って欲しいのだ。ちなみにアメリカなんかのクルマのコマーシャルは、平気でそういうことをする。
映画「キリン」のコンセプトとはまさにそこである。するしないは別として、バイク好きオッサンが堂々と「不良走行」する願望を体現したのである。
面白い世代検証話をしよう。故・尾崎豊の歌詞を今の10代に批評してもらうという実験を、精神科医の香山リカさんとある大学が行った。すると、まったく共感されず、「何を怒っているのか分からない」「ひとりよがりで不愉快」「気持ちが悪い」というようなはっきりとした結果が出るそうだ。
また、若いOLたちからよく聞く話で、酔っぱらうと必ず私たち世代のオッサンが「盗んだバイクで走り出す~♪」とやるあの曲、あれが耐えられないと言う。だから私はそういうお姉ちゃんたちと飲んだ時は絶対に「15の夜」や「卒業」は歌わない。これは私たち世代が上司の歌う、加山雄三や石原裕次郎の歌にとてつもない違和感を感じたのと同じだろう。
「若者のクルマ離れに」みたいなことは、つまり「卒業」を若いOLの前でフルスロットル熱唱してしまうような、「痛いオッサン」のすることなのだ。
しかし、同年代以上の人妻たちと飲んだ時は訳が違う。「卒業」のサビの部分で、同年代の彼女は、昔の彼氏がくれたTDKのメタル・カセットテープを思い出し、涙して、その曲をもう一度歌ってくれと言った。
モテるオッサンか、モテないオッサンか、そこにはネアンデルタール人とクロマニヨン人くらいの違いがある。あなたはどっちだ。

デカいバイクに乗っていると、若いですねとか、元気ですねと言われることがある。それは大間違いだ。ヘルメットは脱毛を促進し、長距離を走った後は腰が曲がっている。きっと乗るたびに半年くらいずつ寿命を削っていると思う。しかし歳を重ねるほどにバイクが楽しくなってくるのだから困ったものだ。
44歳を半分過ぎ、泣いても笑っても折り返し地点は過ぎ去っている。
自らを振り返ると良いことと悪いことは「半々」ぐらいだと理解し始めた。その割合は全体比からしたら相当幸せな部類であるとも分かっている。御の字というやつだ。
そんな立ち位置の私は、色々な物を歳相応に得てもいるが、同時にハッキリと大きな物をそれ以上に失い始めている。
多岐にわたる喪失物は、物質的なもの、肉体的なもの、精神的なものと枚挙にいとまがない。
最近25年くらい前の写真を見て心底驚愕した。そのフレームの中で笑っている私に感じたことは、失った若さというよりも、男の子を授かっていたらこんな子供だろうなというものだった。ちなみに実在する長女とその写真の自分は3歳しか違わない。当然であろう。
同年代の仲間同士で大酒を飲むと、ボーイズトークはおのずとフルコースとなる。
「①仕事の会話→②不景気→③捨てきれない夢→④品性下劣系→⑤健康」
①~④は多少の順番の入れ替わりあるものの、最後に⑤が必ず来る。ちなみに若い時はそれらと全く趣が違っていたはずだ。
「①夢⇄②品性下劣系」
この二つのみが繰り返されるだけだったはずだ。再生と破壊のみが繰り返される純粋世界。
健康についてなど誰も口にもしなかった。その変わり様に自ら恐怖したときもあったが、ここ数年は、私はもう完全に諦めている。勘違いしないでほしい、諦めるということは反対に肉体的健康を強く意識しているということだ。
若さの泉が枯れ果てたことを受け入れ、健康を意識した食生活や生活習慣、適度な運動などを嫌々ながら受け入れているということだ。
年寄り臭い言葉を羅列してしまったが、若さの泉が枯れ果てたことを知ったということは、反対に新しい「泉」を掘り始める切っ掛けだと思っている。
考え方の違いだ。30代、その枯れやすい泉に頼り過ぎていたと気が付いたのだ。そこから自由になれた今、やっと次の泉を掘り当てたような気持ちになっている。
「老人力」という言葉が少し前に流行ったが、「中年力」というようなものなのかもしれない。10代から20代への弾けるようなエネルギー感の残像に縛られ過ぎていた30代とやっと決別できたということだ。遥かに冷静で虎視眈々とした視点で物事を見られるようになった。
そういう変化を極端に嫌う仲間もいる。いつまでも昔と何も変わらぬままでいようと、行動や服装まで、執拗なまでに若さを意識し続ける。
年寄りじみるよりか幾分か良いとは思うが、そんな輩がとても「痛々しく」感じられるときがある。
どんなに若作りしても、化粧を重ねても、本当の若さは再現できるはずもなく、中年女性がセーラー服を着ているかのように、どこか妖怪じみた奇怪なものになっていく。
犬を飼い、その終生を供にすると分かることがある。犬の一生は短く、故に人間の一生よりも色濃く成長と老年変化が見られる。
生まれてほぼ一年で成犬になり、7歳くらいである転機を迎える。今まで当たり前のように飛び越えていた段差に引っ掛かったり、それを飛び越すことを嫌がるようになる。犬の1年は人間の7年くらいと言われるので、ちょうどその年齢が人間でいうところの50歳あたりだ。
「半年前まではあんなに元気だったのに…」しかしその半年は人間でいうところの40代前半と50代の体力の差があるのだ。
7倍の速さで老いていく犬の姿に、私は人間の一生を重ねてしまった。7倍とはいえ、きっと自分の一生もそんなものである。抗うよりもその時間をどう受け入れるかの方が大事なはずだ。つまり、抗っているような暇自体がないのだ。
今の自分に興味を持たず、昔の自分の再現ばかりに終始していては、反対に老化を早めるようでもある。
数年前にとあるバイクメーカーが、バイクに乗っていると「若返る」という科学的データーを発表した。笑止千万。「乗れば」若くなるのではなく、若さがあるからバイクなどという不条理なものに「乗る気」になるのである。また私たちバイク乗りは、抑えきれない何かを確かめるようにバイクに跨る。何かを得ようなどとは思ってもいない。ましてや若さの泉を求めるなど
どんなに屁理屈を並べても、バイクなんてものは「愚の骨頂」なのだ。自分の子供には絶対に乗ってほしくない。
こだわり続けているのは青春や若さへの渇望ではなく、今の自分と激しく向き合うためだ。